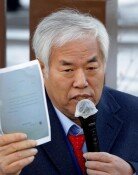大海原で、藁で編んだ人形や船を引いていく漁船が水平線に向かって進む。雲に太陽が隠れて少し暗いこの瞬間の安らかさが伝わってくる。厄を乗せた藁船を捨てるために沖に出てきたためか。漁師の後ろ姿まで安らかに見える。
写真家の故金秀男(キム・スナム)氏(1949~2006)が1985年、全羅北道扶安郡(チョンラプクト・ブアングン)の蝟島(ウィド)近海で撮った白黒写真だ。蝟島の伝統の祓いの儀式を水上で捉えた。展示場の片方を埋めたこの作品は、見れば見るほど観覧客の心をつかむ妙な魅力がある。昔から先祖がお祓いをしたのも、結局は生きている人の心を満たすためではなかったのか。
国立民俗博物館が今月6日から特別展「金秀男を語る」を開いている。昨年、金秀男氏の遺族が寄贈した17万点余りのうち代表作100点を厳選して展示した。民俗博物館が写真家の作品アーカイブを寄贈され、デジタル作業を経て特別展を開くことは多くない。写真家の金秀男氏が韓国の民俗分野に占める地位がどれほどかを物語る。
東亜(トンア)日報のカメラマンを務めたこともある金秀男氏は、1973年から国内各地の伝統の祓いの儀式の写真を撮り始めた。経済発展と近代化で消えていく伝統文化を記録に残さなければならないという使命感が発端だった。彼は単に写真に撮っただけでなく、金仁会(キム・インフェ)延世(ヨンセ)大学名誉教授、黄縷時(ファン・ルシ)カトリック関東大学教授とチームを組んで、地方ごとの祓いの儀式を体系的に記録、整理した。約10年にわたるこの膨大な作業は、「韓国の祓い」(全20巻・ヨルファダン)の発刊で花を咲かせた。
金秀男氏の写真の魅力は、祓いの儀式に参加する平凡な人々の率直な話を忠実に盛り込んでいる点だ。これは、1982年作「ヨシハルマダン、ヨンドゥン儀式」でよく表れている。済州市旧左邑(チェジュシ・クジャウプ)で撮影されたこの連作では、「クサムシンハルマン」(済州の土俗信仰で子供たちに害を及ぼす神)の役割をした「シムバン」(巫女を指す済州の方言)が町の人々に嘲弄される様子と「サムシンハルマン」(子供をさずけて見守る神)の号令で村の外に追い出される姿がユーモラスに表現された。特に追い出される「クサムシンハルマン」が杖をついて丘を越える場面は、広い空とオーバーラップし、求道者の感じまで与える。6月6日まで。02-3704-3248。
김상운 キム・サンフン記者 기자sukim@donga.com