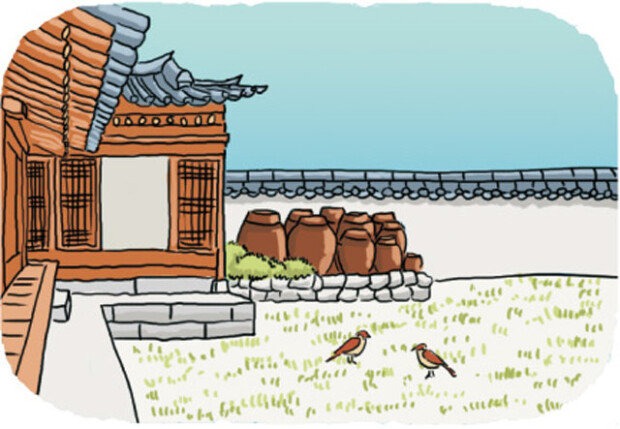
慌ただしかった友だちの足が途絶えると、家の中はスズメの罠を仕掛けてもいいほど寂しい。主人がすることもなくぶらぶらしているから、客をもてなすこともなくなった子供さえ仕事をやめてしまったようだ。春雨が降るや、家の内外が雑草で覆われて落ち着きがない。司馬光は、政治改革をめぐって王安石を中心とした新法派と激しく対立し、そんな中で激しい官職を巡る浮き沈みを経験した。彼が15年間にわたって洛陽に隠居し、「資治通鑑」の執筆に没頭できたのも、ひょっとすれば政治的挫折がもたらしたこうした「暇」のためだったのかもしれない。内心、炎涼世態(権勢のある時はへつらい、零落すれば冷視して顧みない世俗の情態という意)を追う冷たい人情のせいかもしれないが、そのために生活はむしろ暇になったと話す余裕の裏に、詩人の嘆きではない嘆きがにじみ出ている。権力の前で朝改暮変(朝に改め、夕方に再び変える意)するやるせない友情に対する愚痴のようでもある。
「スズメの網」の比喩は、司馬遷が「史記列伝」で紹介した漢の翟公の言葉に由来する。翟公は自分が官職にある時は、お客さんが家の中をいっぱい埋めておいて、官職から退くと、「門の外にスズメ網をおいてもよさそうだ」と嘆き、門に一つの文句を書いて付けた。人は死んでから生き返ったり、貧乏から裕福になってみないと、付き合いの情と態度を把握できないという警告だった。「権力や財物を失うと、訪ねてくる人も少なくなる」という成語「門前雀羅(門の前でスズメの網を張る)」はここから出てきた。門前市を成すとは正反対だ。
成均館(ソンギュングァン)大学名誉教授







