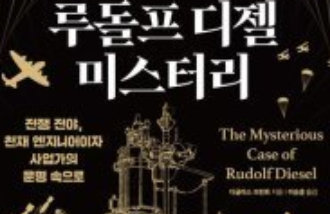学問や技術分野の専門性に対しては、社会では依然尊重しているようだが、文化や芸術分野では状況がだいぶ様代わりしたように思える。とくに文学はその専門性が解体されつつあるのではないか、と思われるほど無視されたり、非専門性から挑戦を受けている。
まず、目につくのは生産部門での非専門性の拡大だ。いまだに文壇というものが存在しており、文学生産者としての専門性を検証する各種の登壇制度が維持されているにもかかわらず、その権威が脅かされて久しい。
むしろ最近よく経験するのは非専門性の躍進だ。もう少し誇張すれば、だれでも小説を書けばそれがそのまま小説であり、詩だとして書けば、それがそのまま詩になる世の中になっているという感じがするのだ。
もちろんこうした現象をあえて否定的に見たり、批判する理由はない。観点を変えれば、こうした生産者の増加は専門性のすそ野拡がりにつながり、文化の階層を多様化するのに貢献しているとも考えられる。また、既存の検証制度が持つさまざまな弱点を補完する働きもある。そもそも専門性を検証する制度自体が無理なことなのかも知れない。
だが、流通と消費に関連した検証制度である批評にいたっては、問題が違ってくる。生産された文学作品の品質を評価する批評は、「文学」という制度が続けられてきた歳月や広がりに値するほど由緒深く、多様な原理について専門的な知識を要求している。批評とは、こうした知識を適用させて、客観的な基準を設定できる感覚と資質がその基盤とならなければならない。
批評はまた、読者の主観的な解釈とは違って、批評家個人を超えて、多数の消費と流通に影響を与えるということを最初から念頭に置いているという点でも、専門性は尊重されるべきだ。
ところが、最近とみに致命的な挑戦を受けているのがまさにこの「批評」部門ではないかと思う。マスコミが自分の性向や利益のために、専門性が検証されていない雑文を適当に掲載して批評とうたっているかと思えば、私的で主観的な読者の解釈権を大衆運動の形式に拡大させて、批評が消費と流通に影響を与える重要な働きを代わってすることもある。
ある人は自分の分野ではこれといった著述一つないながらも、そうした雑文だけでの批評家よりももっと批評家的な名声と追従者を得たりした。
だが、とうてい理解できないことは大多数の批評家がこうした現象を傍観してきたことだ。どの社会にもありがちな、文化的なパパラッチやストーカー程度のものと見ているかも知れないが、その結果は非常に深刻だ。ここ数年自分の政治的な立場や趣向に合わない何人かの作家を執拗に攻撃し、読者との溝を深めさせることでおいしい思いをしてきた、ある非専門批評家がとうとう「文学界」全体を「手なずける」として公言してはばからなかったこともそうだ。
幸い、いくつかの最新号の季刊紙では、専門性の検証を受けた批評家がえりを正して応戦する様子が掲載された。だが、非専門的な言葉と論理の対応に追われてか、用語の俗化と感情的な論理は、専門性の危機さえ感じられた。非専門性の弊害が読者を誤導する水準を超えて、批評行為自体まで及んだケースではないかと思う。
ある人は文化の専門性に関する是非は、パトロン(文化後援者)の選択にかかっているという。すなわち、文化生産者や流通管理者が議論する性質のものではなく、現代のパトロンである消費大衆(読者)の選択が決定するという意味なのだろう。理に適っている。すべてが商品化され、市場構造の枠組みに編成されつつあるこの時代に、文化とて例外では有り得ない。読者がもうこれ以上高品質、専門性を求めなくなるのも、いくらでもありうる文学的な状況だ。
だが、社会全般で進みつつある文化の専門性解体がこうした時代の流れとは関係なかったり、もしくはその流れに乗じた故意による意識のわい曲と誤導に過ぎないとすれば、安心はできない。たとえば、政治的な平等権を文化にも適用させて、専門性の解体を文化的な平等権の成就だと大衆を錯覚させることがそうだ。かつてどの時よりも平等権に敏感になっている大衆の好みに合わせる戦略としては立派だが、世界史のある不幸な時期のように、政治過剰な時代に見られた文化の不毛をもまた、思い浮かべさせるからだ。
李文烈(イ・ムンリョル)小説家