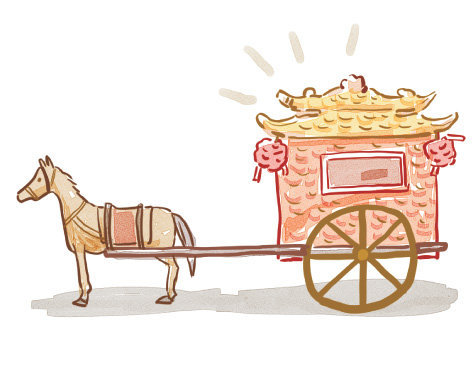
科挙制の以前、官吏の登用は地方官が推薦した孝行息子や清廉な衙前(朝鮮時代の下級官吏)らを中央で審査して決めたり、国家に功績を立てた一族の子弟を特別採用したりすることが大半だった。特に、門閥重視の風潮が広まった魏晋時代には、当事者の能力に関係なく一族の威勢で官吏になるのが通例だった。しかし、科挙制は、一族の背景に関係なく普通の家のソンビ(士人)も純粋に能力だけで官吏になることができる夢の舞台だった。各地の秀才が集まり、いつ及第するかもわからぬ試験にしがみつくソンビも少なくなかった。「進士科は五十で及第しても早い」という言葉はそのために生まれた。唐の高宗(コジョン)の時に宰相まで務めた薛元超も、一生の心残りを「進士に及第できなかったこと」と言うほどだった。「門蔭(一族の余徳)」で官職に就いたことに対する痛切な自責だったのだろう。
科挙の試験はそれほど難しいものだったので、10年間受験した詩人が及第直後、喜んで声をあげながら小躍りしたのは当然のこと。詩人が見るに、及第は官吏が昇進を重ねることよりも難しい。鼻高々に故郷の友に「両目を大きく開いて私を見よ」と叫ぶ。もはや自分を「刮目して相待すべし」というのだ。一時詩人の才能を認め、科挙の受験まで勧めた李紳が偶然この詩に接し、忠告の詩一首を送った。「偽金を真金に鍍すもの。真金なら鍍せず。十年ぶりに長安で及第したが、空腹でなぜそれほどまでに飾り立てるのか」。







