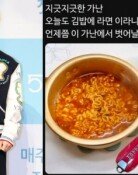2004年3月17日、アテネ五輪のサッカー最終予選でイランとのアウェー戦を控えていた金浩坤(キム・ホゴン)監督は標高1800メートル高地の中国昆明で1週間のキャンプを行った。
当時、一部では「何のためにもならない訓練を何しにやっているんだ」という非難が降りかかった。運動生理学的に、高地では少なくとも3週以上の訓練をしないと、体に意味ある反応は表れないからだ。
論争はあったが、韓国は1220メートル高地のイラン・テヘランで1−0で勝った。金監督は、「科学的には大した為にはならないことは知っていたが、選手たちが高地を体験したのとしていないのとでは雲泥の差がある。心理的効果を狙ったもので、成果があった」と話した。
南アW杯を控えて坡州(パジュ)サッカー代表チームトレーニングセンター(NFC)に設置された低酸素室の効果をめぐって論争を起きている。低酸素室と低酸素テントを無償で貸した側では、多様な実験の結果、1日1時間ずつ休むことだけでも十分効果があると言っている。
しかし一部の学者は、「休憩時間の全部を過ごすか、そこで練習をしてこそ大きな効果が得られる」として代表チームが実施している低酸素室の効果に疑問を示した。
厳格な科学的知識からすれば、現在代表チームが行っている低酸素室での休憩の効果はさほど大きくないものかもしれない。しかし04年の経験からも分かるように、心理的な効果は大きいというのが専門家たちの見解だ。低酸素室での休憩の効果を否定する学者も「フラシボー効果」は認めており、心理的な面での効果はあると見ている。
では何が問題なのか。今の代表チームは、練習期間があと1ヵ月も残っていない。高地練習ができる状況にもいない。高地適応でなくてもするべきことは山ほどある。リーグを終えた欧州組は休憩が必要だ。そのなかで、国内組との調和を図る戦術練習もこなさなければならない。フィジカルトレーニングもある。今の代表チームは可能なすべての方法を動員して、選手たちのコンディションを引き上げようとしており、そのうちの一つが低酸素室の運営であるに過ぎない。
yjongk@donga.com