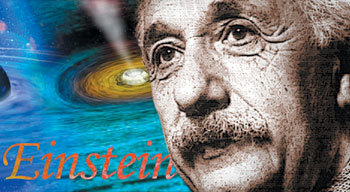
「アインシュタイン、私の世界観」/アルベルト・アインシュタイン著/ホン・スウォンの他訳/407頁/2万2000ウォン/ジュンシム
これまでわれわれが彼に借りがあると考えてきたのは、彼の「宇宙観」だった。しかし、この本で彼は「世界観(Weltbild)」を語っている。
ここで読者は、物質とエネルギー、光速と時間に没頭してきた科学者が、人類の前に差し出した実践的智恵に出会うことができる。この本は、寄稿と演説などから抜粋した、ある科学者の「参加の記録」だ。彼のペン先は、素朴だが執拗だ。そして、そのペン先は、現代史を狂気と破壊で塗りつぶし、個人と平和の尊さを脅かしてきた「集団主義」に向けられている。
本の内容に入る前に、哲学者のオルテガ・イ・ガセットが『大衆の反逆』で提起した問題を想起させることができる。なぜ「限られた専門分野」に没頭してきた科学者が、社会倫理的な問題を論じるのか。そうする権威を与えられることが妥当なのか、と。
この質問に直接答えたわけではないが、アインシュタイン自身はこう述べている。「沈黙を守る場合、共謀への責任感を覚えるときのみ私は大変稀に意見を述べてきた」と。彼の書簡の中で「知的で倫理的な作業(行為)」という表現が頻繁に登場するのは、彼が科学者の職分を世界倫理的なものと認識したことを意味するものでもある。
彼の「世界観」は、個人を通して、初めて国際政治と人類に向かって進む。人生の目標は何なのか。それは、他人からより多くのものを受け取る能力ではない。他人に与えることのできる能力が、人間の価値を決定する。自分の人生が、他人の苦労の上に成り立っているものであるだけに、それを返すことが人生の目的になるべきだという。
彼が言う「他人」の中に、排他的共同体や集団は介在する余地がない。残るのは個人と全体としての人類共同体のみである。「個々人だけが思惟することができ、個々人にだけ霊魂が与えられる」。
「個人」に対する彼の関心は、さらに「体制」に対するものに移行していく。「人間が日々の生活必需品を調達するのにすべての力を消費していては、他の形態の自由も、何の役にも立たない」。「資本主義の無限競争は個人の社会意識を麻痺させる危険をはらんでいる」。こんな指摘が災いして、彼は1950年代のマッカーシー旋風の中で除去の脅威に追い込まれた。
しかし、個人に対する彼の愛情が全体主義と妥協できないことは当然だ。彼は、第二次世界大戦の以前からファシズムとボルシェビズムの人間性抑圧を同様に叱咤していた。「社会主義は自分の側に立っていないすべての人々に、邪悪な人間と言う烙印を押す」。何よりも計画経済は「個人を奴隷化」させることを彼は忘れなかった。
一人立ちした人間の尊さを強調してきた物理学の巨星は、戦争が終わった後、全世界の尊敬と嘲笑を同時に招いた宣言を行う。すなわち、米ソ英の3国が協力する「世界政府」の樹立を求めたのだ。世界安保のために、すべての軍隊を多国籍軍にして再配備しようというものだ。
「万人の万人に対する闘争を避けるため、個別国家は自決権を犠牲にするしかない」。しかし、これに対する世界の、とりわけソビエトの反応は冷淡なものだった。世界政府とは、全世界に投資対象を拡大しようとする資本家たちの陰謀だとした。彼の理想論があまりにも時代を先駆けしたのだろうか。
1952年、新生イスラエルの初代大統領職の提案を受けた彼が、一言で断ったのも当然の結果だった。彼は、ユダヤ人の「民族国家」とは「民族主義」から受けた苦痛を逆に世界に対して返そうとするものと写ったのだろう。
今年は、この本の原著が出版されて50年になる。彼と同時代を生きた作家シュテファン・ツバイクは、自分達世代を「進歩の千年王国から奈落に落ち、すべての人類が徐々に経験したことを、一瞬にして嘗めた世代」と規定した。世代の痛みは、その世代の智恵を生んだが、その後の世界の「文明」地域が半世紀の平和を味わう間、人類は自身の破壊的な本性に対する警戒を忘れていった。「一つずつの人間」と「すべての人間」の名で平和を訴えた科学者のメッセージが今も新しいのは、そのためだろうか。
gustav@donga.com







