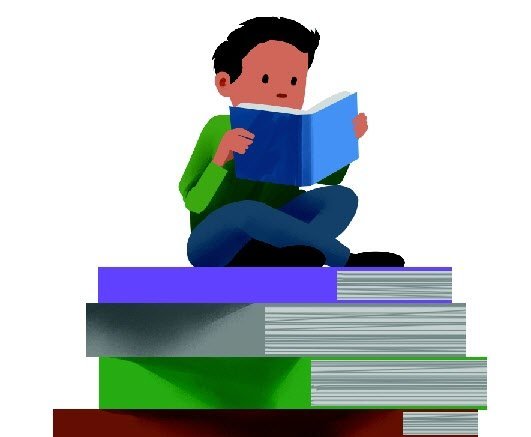

「誰も、本屋では決して寂しくない」(ペネロピ・フィッツジェラルド著「ブックショップ」、1978年)
町内の常連の古本屋の出入り口に、上記のような文章が書かれていた。本屋のオーナーが作ったのかと聞いてみたら、違うそうだ。「映画で見たものだ」と言って、その内容を聞かせてくれる。
「夫と死別した中年の女性が、閑静な海辺の村に一人で本屋を開こうとします。夫に初めて会った思い出の場所です。しかし、よりによって本屋にしようとした建物は、地元の有力者が欲しがっていたところだった。それで外部の人である彼女のことにあらゆる邪魔をする。彼女は屈しません。幸い村で彼女を助けてくれる人がいるので…」
映画の話を聞いてみると、ストーリーが社長の話と似ている。引退後、何も持たず漠然として寂しかった時期。オーナーも古本屋をオープンする時、困難があった。幸いなことに、彼には悪い地元の有力者の代わりに助っ人がいた。既存に定着していた町内の複数の本屋が、彼の力になってくれたのだ。仁川(インチョン)の長い歴史の古本屋町であるペダリのサムソン書林が無くならなかったことに関する話だ。
オーナーが話した映画の原作は、英国作家のペネロピ・フィッツジェラルドの小説「ブックショップ」(1978年)だ。小説家の自伝的な話が盛り込まれているという。作家の履歴がユニークだが、彼女は61歳で初の小説を出した。病気の夫を慰めようと書き始めたのが、職業になったという。遅ればせながらのデビューだったが、イギリスを代表する作家になった。
本屋のお客さんなら誰にでも、オーナーはインスタントコーヒーをいれてくれる。お客さんと言っても一日中少なく、それで本を買う人はさらに少ない。むしろ行き場のない町内のお年寄りたちが、暖かいぬくもりを求めて本屋を訪れる。やることのない人も、しばらく本をめくりながら息を整える。本を買わなくても、本屋は誰にでも避難所になってくれる。まるで本で作った公園のようだ。片手にコーヒーを持ってのんびりと本を読んで、出入り口を眺める。ふと文字はこんなにも読まれる。「誰も決して寂しくなってはならない」







