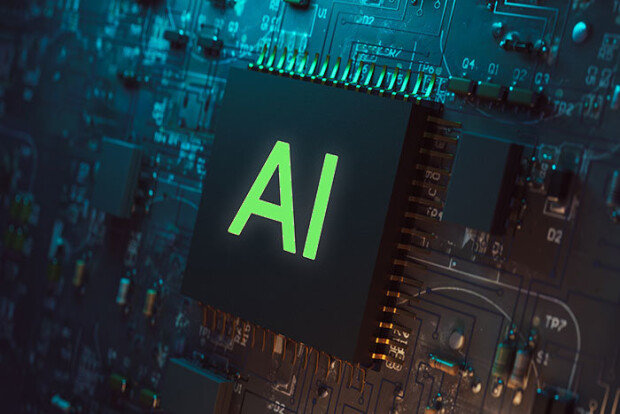
世界主要国が、人工知能(AI)の人材確保戦を繰り広げている中、政府はAI融合分野の国内外の博士研究員(ポスドク)400人を確保するため、5年にわたって3000億ウォンを投入する。米国のトランプ政権の研究費の予算削減で起きた研究者の米国離れ現象を、科学技術人材の「リショアリング(国内復帰)」のチャンスとして活用する狙いも背景にある。最近、日本政府も、1000億円(約9500億ウォン)の緊急資金を投入して、米国を離れる人材の確保に乗り出している。
科学技術情報通信部と国内4大科学技術院(KAIST、UNIST、DGIST、GIST)は15日、AI融合分野の8の「イノコア研究団」を選定し、国内外の博士研究員400人の採用に乗り出すと明らかにした。
博士研究員中心の集団研究を通じて、優秀な青年研究者の成長と国内産学研の研究生態系への進出を支援するのが目標だ。今回の事業は、緊急性を考慮し、今年の補正予算として300億ウォンが反映され、その後も5年間で3000億ウォンを投入する。事業を通じて選抜された博士研究員には年俸9000万ウォンを保障し、1人当り6000万ウォンの研究費も支援する。優秀な人材が海外より高い水準の支援を受けられるよう、研究団に参加する企業や他の研究課題をマッチングする追加支援などを推進する方針だ。
政府は、中国発「ディープシークのショック」から見られるように、博士研究員が先端技術研究の主体だと見て、支援を積極的に拡大することにした。科学技術情報通信部の関係者は、「ディープシークの主要アルゴリズム開発者の平均年齢帯は、20代後半から30代前半で、博士号を取ってから2、3年目に研究成果を創り出した」とし、「我が国は、博士研究員を『臨時職』として認識する傾向が強く、支援が足りなかった」と話した。
米マサチューセッツ工科大学(MIT)は、専任教員より1.4倍多い博士研究員が採用され、最先端研究で中心的な役割を担っている。しかし、国内4大科学技術院に採用された博士研究員は、専任教員数の半分に過ぎない。また、4大科学技術院の博士研究員の平均年俸は、MITの41%の水準にとどまり、国内博士号を持っている人が米ポスドクに就職するなど人材の海外流出が多いのが現状だ。
4大科学技術院は18日(現地時間)、ハーバード大学とMITのある米ボストンを皮切りに、20日はニューヨーク、23日はシリコンバレーで現地の博士研究員の採用説明会を開催する。このような内容をネイチャーやサイエンスなどのグローバル学術誌と採用プラットフォームのリンクトインにPRし、海外の参加協力機関と韓国人科学技術者のネットワーク(KOSEN)、在外韓国科学技術者協会、韓国人学生会なども活用する方針だ。
チャン・ウンジ記者 jej@donga.com







