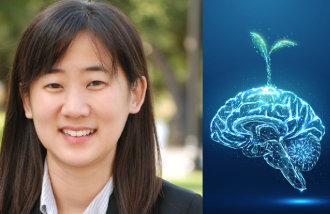テキストヒップの時代に薄くなった本、日常に染み込む読書
テキストヒップの時代に薄くなった本、日常に染み込む読書
Posted February. 22, 2025 09:00,
Updated February. 22, 2025 09:00
朝鮮後期の実学者、李德懋(イ・ドクム)がソンビ家の礼節と文化を考察した「士小節」には、本を扱う私たちの祖先の厳しい姿勢がよくあらわれている。自らを「看書痴(本ばかり読むバカ)」と称したほど本が好きだった彼は、「ただざっと読んでから、広く見てたくさん読んだと言って騒いではいけない」と知的な見栄を警戒する一方で、書物自体をどのように扱うべきかについても几帳面に触れているのだが、ドキッとする部分が多い。
「本を読む時は、指に唾をつけてページをめくるな。爪で線を引かないで…枕の代わりにせず、肘で支えるな…掃除をするところでは本を開いてはいけない。本を投げたり、ランプの芯をかきあげたり、頭を掻いた指でページをめくることなど考えるな」
見習うべき正しい習慣ではあるが、この基準に照らしてみれば、現代人の中で誰もまともな知識人とは言い難いのではないかと思う。年間韓国で発行される新刊の種数が6万種を超える時代、本の物性そのものをこのように神聖視する人はほとんどいない。
しかし皮肉なことに、多くの韓国人は心理的には依然として李德懋が警告した以上に本に慎重に接しているようだ。成人の平均読書率は年間3冊程度、10人中6人が一年に1冊も本を読まない韓国の低い読書率を見ると、読書という行為は身近な日常というよりは、大きな決心をして行う恒例の儀式のように悲壮に感じられる。
最近、書店街では軽く読める薄くて小さな本が次々と出版されている。軽長編シリーズが増え始め、今は「ウィピックシリーズ」「ダルダルブックダ」のように、短編小説一つだけで単行本として作り出すシリーズまで数多くできている。数年間にわたって書いた短編小説6、7本を集めてこそ1冊の本になると考えていた以前の基準から見れば型破りといえる。月ごとに新しく出るエッセイシリーズ「タイムリー」のようなものもある。旬の食べ物のように、本も旬の読み物を楽しめという意味だそうだ。本と雑誌のハイブリッドみたい。
息とサイクルが短くて軽いこのような本について、一部ではショートフォームに慣れて本を読まない映像世代を捕まえるための苦肉の策と見たりもする。だが、最近若い読者を狙って薄くなる本は、単純に本の大きさと厚さが減っただけでなく「本ならばこうでなければならない」という固定観念も共に破るという点で目が行く。
国民読書実態調査によると、本に近寄りにくい理由の中で、「仕事のために時間がなくて」(24.4%)と同じくくらいに多いのが、「本以外のメディア(スマートフォン・テレビ・映画・ゲームなど)のため」(23.4%)だった。読書という行為自体が能動的な思考を要求することはあるが、本を読むことが他のコンテンツとは異なり、「覚悟して」やらなければならない特別なことのように感じられれば、本を選ぶことも、読むこともさらに難しくなる。どんなきっかけであれ、読む楽しさを享受した人々が自主的な読書、深みのある読書の世界に進む。テキストヒップが流行して登場する薄い本が、読書を日常に染み込ませる良い契機になることを期待する。