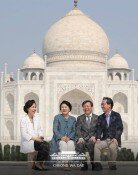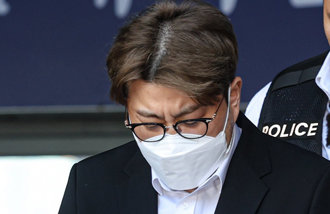欧州や日本などの福祉大国のパラダイムが変わっている。「ゆりかごから墓場まで」という言葉が象徴するように、普遍主義や連帯原則に則って運営された年金や健康保険制度を、恩恵者や個人の利益、市場原理の充実した制度へと変えようとしている。
言い換えれば、普遍的福祉から選別的福祉への転換だ。全ての児童・生徒への無償給食や、全国民の無償医療、無償保育を掲げる、韓国の野党や進歩団体の要求とは相反する動きだ。
福祉大国が方向転換する背景には、無視できない厳しい現実がある。経済は常に成長するのではなく、寿命延長により、人口の急速に高齢化が進むと、高成長多出産時代の健康保険や年金制度は、国家財政を圧迫する要因となった。
福祉というプレゼントは、国民に抱かせる時は甘かったが、再び取り上げようとすると、痛い見返りを払わなければならない。昨年、フランスのニコラ・サルコジ政府は、60歳の退職最小年齢を62歳へと引き上げ、年金全額受け取り時期も、65歳から67歳へと遅らせ、大規模のストやデモに苦しまれた。フランスは同制度を今年1月10日から実施している。
ギリシャやスペイン、イタリアは昨年、財政危機に落ち、ユーロ経済圏全体を脅かす「問題国家」と名指された。ポルトガルやアイルランドを加え、いわば「PIIGS(ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ、スペイン)」という新造語も出た。
これらの国々が国家不渡り危機に陥った直接的なきっかけは、08年のグローバル経済危機だった。しかし、根本的には普遍的保障中心の福祉国家へと急激に転換し、経済規模が耐えられなかったというのが、専門家らの見方だ。
政治圏の安易な対応やポピュリズムも、問題を悪化させた。少なく受け取り、多くを与える福祉体制は、誰が見てもメスを入れなければならなかったが、国民の反対にぶつかり、あるいは国民からの反対を恐れ、現実に安住した。
全人口の23%(260万人)が年金で生活しているギリシャは、昨年、財政が破綻してからようやく、年金受け取り額を平均7%削減する年金改革案を、労組の反発を押し切って確定した。スペインも、出産手当を廃止し、定年を引き上げるなど、改革に乗り出した。
それとは逆に、いち早く福祉改革に成功した国は、政権が揺らぐことはあっても、改革を強く推し進めたという共通点がある。この過程で改革を主導した政権は、その大半が失脚した。改革の成果は、次の政権になってからようやく現れた。
高負担高福祉を選び、福祉天国と呼ばれたスペインは、1985年以来議論を繰り広げ、1998年に新年金法案を可決させた。保険料支払いとは関係なく、提供する老齢基礎年金を減らし、所得に応じて年金額を決める制度を導入した後、需給対象者を減らした。同法案を主導した政権党は1990年代初頭、総選挙で惨敗し、政権が崩壊した。
このように福祉は最も敏感な政治話題だ。そのカギは、現世代を次世代に健全に引き継がせる持続可能性だ。そのような観点から、よい福祉制度の最大の敵は、目先の票獲得ばかりに拘る政治家であるかも知れない。彼らは国民がけん制しなければならない。持続可能な福祉に向け、努力する国の昨今を探ってみたい。
viyonz@donga.com tesomiom@donga.com