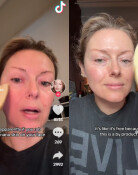23歳で「阿房宮賦」を詠って、国の盛衰興亡の理を説いた杜牧。始皇帝が統一した秦が滅亡したのは、贅沢と享楽に陥った朝廷のせいであって、決して天下の大勢のせいではないと言った。虚弱な晩唐の朝廷が、この歴史の教訓を忘れれば、不幸は繰り返されるだろうという忠義心を詠いあげたのだ。当時、科挙試験を主管する高官にこの名文が知らされ、 杜牧は若い年で官職に就いた。ところが、彼自身も風流と享楽に酔って抜け出すことができなかった。自ら、「揚州で過ごした10年間の歓楽の夢から覚めたら、残ったのは青楼での不幸せな名声だけだな」と嘆いたほどだ。
詩は、節度使や兵部尚書などを務めた李願という役人が洛陽に滞在した時、ちょうど監察御史を務めていた杜牧のために開いた宴会で作った作品。詩人はまず、「どなたが、この体を招待されたのか」と平然と聞く。皆が知っているのに、わざと自分の存在を誇示しようと、一度虚勢を張ってみたのだ。いきなり座中は、詩人が吐き出した「たわ言」で、驚くべき状況に変わる。「この宅に、紫雲というきれいな歌姫がいるそうですが、その子を私にください」。風流客の突拍子もない傲慢さに、主人と客、「両側に立ち並ぶ美女たち」がびっくりしたのは言うまでもない。この要求はもちろん断られ、気まずい境遇を免れようとしたのだろうか。詩人はずうずうしく、この詩一つで照れくさそうな状況を押しつぶそうとしている。