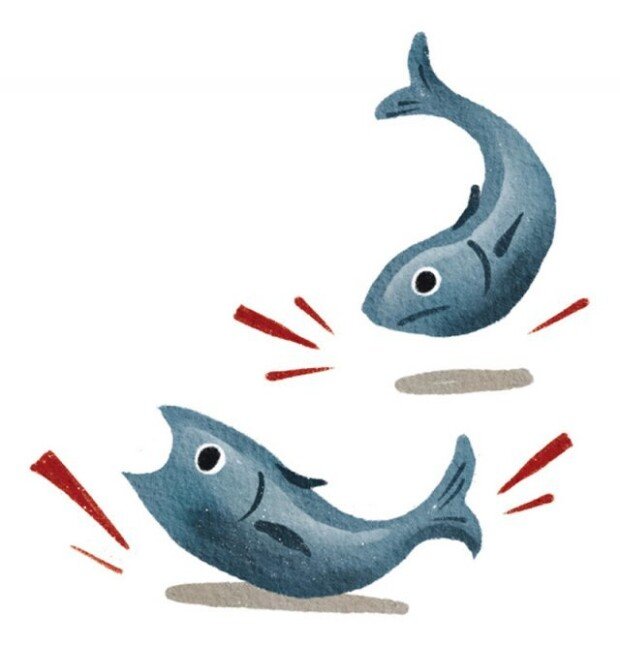
山には寺があり、寺の中には木魚がある。大きな木の魚が山風に当たって揺れる姿を見ると、不思議に思わざるを得ない。山に何の魚か。魚と仏は何の関係があるのか。古い魚の伝説のためだという言葉もあり、魚のように目を閉じず精進しろという意味ともいわれる。この木魚が小さくなって丸くなれば、私たちが知っている木鐸になる。だから僧侶たちが叩く木鐸とは、遠い昔、遠い海の魚から来たということだ。
このような事情のためだろうか。木鐸を見ながら魚を思い浮かべる私たちの前に、ペ・ハンボン詩人は似ていながらも全く異なる考えを提示する。彼は、魚から木鐸ではなく「肉鐸」を取り出す。明け方の魚市場、生きている魚たちが陸に出てきてぱくぱくする。全身で床を叩きながら音を出すのが、まるで体で打つ木鐸のようだ。人生の最も悲惨な瞬間は、最もつらい瞬間であり、最も生きたい瞬間だ。その時にはできることが多くないだろう。必死になってもがくしかない。詩人は、魚がぴちぴちするその夜明けを、活気に満ちた市場だとか、湧き出る生命力だと表現できない。床を打つ全身の叩き方から、自分自身を見たからだ。
私たちは詩で魚を見たが、魚だけではなかった。詩の中には生臭いにおいの代わりに涙のにおい、人のにおい、汗のにおいが充満している。「肉鐸」という言葉を今日初めて聞いたが、それについてすでに知って見て体験した気がする。人の話のようだが、結局私に戻ってくる話、これがまさに詩だ。







