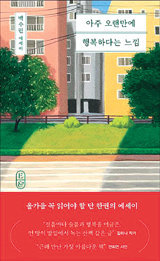
実に「さっぱりした」エッセイ集だ。
最初から最後まで、大げさな出来事などない。「古い町で家を求め、穏やかに暮らしながら色々な縁を結ぶ」。これで内容はある程度説明される。もちろん家族だったペットの「ボンボン」が死んだのは大変だったが…。さっぱりしすぎて、何の面白みもないと言ってもいいほどだ。
しかし、そのような味に惚れて、平壌(ピョンヤン)冷麺を求める人は一人や二人ではないだろう。小説「親愛なり、親愛なる」(現代文学)等を通じて、次々とファン層を築いてきた作家は、エッセイも老舗グルメのように渋い文章に包まれる。たまにもつれる感じもなくはないが、それがまた不思議に中毒性がある。
何よりも文章がさらさらと流れていくが、いつのまにか本を手放せずに嵌っていく。「最近出会った最も美しい本」(アン・ヒヨン詩人)かどうかは分からないが、些細なことからもその質感と重さを見出す目に驚かされる。確かに、あんずを売る露店を広げて、「ブサイクでも甘い」というお年寄りの前にしゃがんで、「ああ、もちろん知ってますよ」と応えてくれる人なら、何でもうなずいてあげたい。
突拍子もないが、本をめくりながら、ふと天文学者カール・セーガン(1934~1996)が思い浮かんだ。「何もない無の状態でリンゴパイを作るには、まず宇宙から作らなければならない」と言ったのか。村の入り口に咲いた名も知らない雑草にも、一つの暮らしと共存と世の中が宿っていることを。時間が止まることはないだろうが、住み慣れた町に長く滞在することを。今年の冬の暖房費は無事に過ぎますように。
丁陽煥 ray@donga.com






