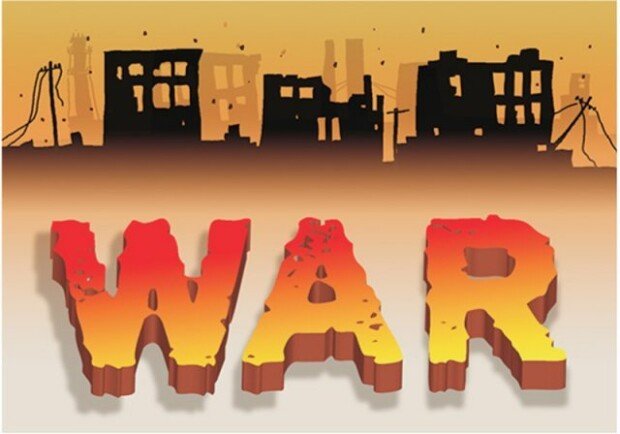
1970年代の話だ。工学を専攻した教授が米国留学から帰ってきた。持ち物を検査した税関員が荷物の中いっぱいの本を見て尋ねた。「先生はなぜこのように革命がお好きなのですか」。理念、政治的信念に敏感な時代だった。数冊の本のタイトルに記されている革命(Revolution)という単語が目に止まったようだ。その本は「交通革命」、「生活革命」といった本だったのだが。英語圏の国家で使う革命という単語の多様な用途を理解できないためだった。
戦争も、日常で誤用され乱用される単語の一つだ。競争ストレスに苦しむ現代人は過度な競争、激しい競争状態を描写する時、戦争という単語を付ける。入試戦争、アパート申込戦争、各種予約戦争、最近は「毎日が戦争だ」という言葉もよく耳にする。
「戦争」という単語には、熾烈さ、殺伐さ、極限の競争状態という意味のほかに、もう一つの重要な意味がある。手段の方法を問わない無慈悲さだ。競争し戦っても、ルールが適用される場があり、ルールを放棄する状態がある。後者が戦争状態だ。それは嘘だ。罠が称賛され、裏切り、買収、約束破棄が当然で、誤爆と誤発弾で民間人が犠牲になり、現地調達、恐怖感の造成、抗戦意思の放棄という戦略的理由で都市を破壊し、民間人と子どもを虐殺しても目を背けさせるのが「戦争」という単語の魔法的な意味だ。
ジュネーブ条約、典範、SNSを通じた世界の人々の目と糾弾、戦争に国際的なルールをつくってそれを守ろうとする努力は意外にもそう長くない。第2次世界大戦は、18、19世紀に比べれば人道主義が成長したように見えるが、戦争の片方では爆撃、原爆、ガス室で類例のない大量殺戮が起こった。
SNSが猛威を振るう21世紀には、戦争のルールが機能するだろうか。皆そう信じたかった。しかし、それは虚像だ。戦争前には正義の人も、戦争が起これば突然変わる。正義?それは私の中にある野獣との戦いだ。







