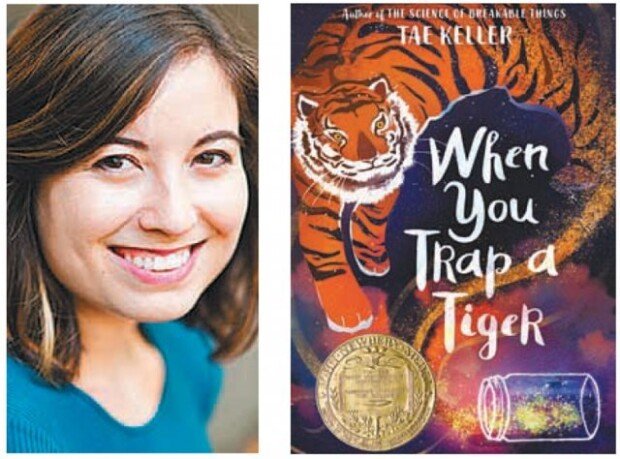
一篇の詩が感情をかきたてる時がある。米大統領就任式でアマンダ・ゴーマンという若い詩人が約5分間朗読した自作の詩「我らの登る丘」がそうだ。
「日が始まる時、私たちは自問する。終わらない影の中、どこに光を見つけられるか」。このように始まる詩で、影は米社会が政治的、社会的に経験した暴力と不信、冷笑と憎悪に対する隠喩的な表現だ。恥ずべき連邦議会議事堂での暴力だけでなく、人種差別、性差別、コロナによる死が全て影だ。それでも詩人は絶望しない。「私たちは嘆いたけれども成長し、傷ついたけれども望んだ」。
歴史を振り返ればそうだ。人間は常に悲しみと傷を克服して生きてきた。歴史と現実を見つめる詩人の目は非常に楽天的だ。詩人が黒人奴隷の子孫であり、母子家庭で育ち、発話障害があったというストーリーによって、詩はさらに訴える力を発揮する。ゴーマンさんがこの詩を書くことになったのは発話障害が理由となった。彼女は外国人ではなかったのに発音が下手だった。特に「R」の発音ができなかった。それで本を読み、2017年には初の全米青年桂冠詩人になり、バイデン氏の就任式で人々の心を揺さぶる詩を朗読した。障害を克服して丘に登った人であるがゆえ可能なことだった。大統領自身も幼い頃、発話障害があった。
これは個人だけのことではない。個人に丘があるように国家や共同体にも登らなければならない丘がある。詩人が影を振るい払おうとした理由だ。「光は常にある。それを見つめるだけの勇気さえあれば。光になるという勇気さえあれば」。なんとか光を探そうとし、時には自らその光になろうとする勇気さえあれば、影から抜け出すことができるという言葉だ。これは米国だけのことではない。勇気は互いに対する不信と冷笑の影に閉じこもっている私たちにも必要なことかもしれない。自らが光になる勇気。
文学評論家・全北(チョンブク)大学教授







