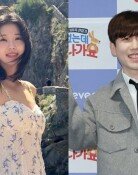ローマ法王ヨハネ・パウロ2世の死は、多くの面で昨年6月のロナルド・レーガン元米大統領の死と比較できる。2人は、1980年代の世界政治を風靡した偉人であり、暗殺計画を奇跡的に避け、世界共産主義没落の隠れた主役という共通点を持つ。晩年に、それぞれパーキンソン病とアルツハイマー病を患った点も似ている。
しかしレーガン元大統領は、世界最強の大国の指導者だった一方、ヨハネ・パウロ2世は、人口約900人という世界で最も小さな国家(バチカン)の首班だった。
米大統領は、エア・フォース・ワンという専用機に乗って多くの記者を連れて動くが、法王は専用機もなく、随行記者は費用を分担しなければならない。また、米大統領は、北大西洋条約機構(NATO)、ロシア、中国、日本、北朝鮮を合わせたよりも多い国防予算で武装した軍事力を持つが、法王にとって軍事力とは110人のスイス衛兵が全てだ。
しかし、ヨハネ・パウロ2世の死は、レーガン元大統領の死よりも大きなニュースになった。これを宗教指導者と政治指導者の差だけで説明することはできない。
ペトロからヨハネ・パウロ2世まで、合わせて264人の法王の行績を書いた「法王の歴史」を読めば、法王の死が大々的な哀悼の対象となった時はまれであった。初期には、迫害を受ける少数派指導者として殉教者が多く、コンスタンティヌス大帝のキリスト教公認以後は、政治的暗闘と金銭的取引きに染まった。
聖カリストゥス1世(在位期間217〜222年)は、詐欺と横領の前科者であり、ヴィギリウス(537〜555年)は石に当たって死んだという。ケレスティヌス4世(1241年)が10人の枢機卿が参加したコンクラーベ(法王選挙会議)で2ヵ月半ぶりに辛うじて選出されたが、17日後に死亡した事実は、法王選出の裏の醜い権力欲を表わす。猛暑の中で進められたこのコンクラーベは、枢機卿の1人が死に、他の枢機卿も死の門にまで至った後でやっと合意した。
数人の情婦との間に少なくとも9人の私生児を産んだアレクサンデル6世(1492〜1503年)は、道徳的二重性の象徴だ。法王に選出されるやいなや「神が私に法王職を贈られたので、心おきなく楽しもう」とふんだんにお金を使ったレオ10世(1513〜1521年)は、放蕩の証人だ。
歴代法王の中で、聖人として推戴されたのは78人、福者として推戴されたのが8人に過ぎない理由も分かる。その中でも、大法王という称号を受けるほど宗教的霊性と政治的指導力を同時に発揮した法王はレオ1世(440〜461)とグレゴリウス1世(590〜604年)の2人だけだ。
410年のローマ陥落、1054年の西方教会と東方教会の分離、1517年マルティン・ルターの免罪符販売批判による新教徒革命、1870年バチカン市(ソウル昌慶宮ほどの広さ)に法王領の縮小…。
このような絶えない危機の中で、法王庁が約2000年も存続できた理由は、世俗権力と「不可近不可遠」を維持した政治外交力にあった。法王は6世紀まで、ローマ・アンティオキア・エルサレム・アレクサンドリア・コンスタンティノポリスの5つの主教の1つに過ぎなかった。しかし、ローマ帝国の分裂後に展開されたローマとコンスタンティノポリス両大体制間のシーソーゲーム、東方教会の分離後も続くヨーロッパ皇帝たちの懐柔と脅迫の中で、生存能力を体得し、一種の組職IQとして蓄積・発展させたのである。
「バチカン帝国」は特に、1870年の教会国家の没落後、過去に焦点を合わせて、いかにしてバチカンが国連よりも強い影響力を確保するようになったのかを分析した。その土台は、陰謀論者たちが言う財力や情報力ではない。世俗的権力を放棄する代わりに、外柔内剛の「ソフトパワー」を育成したところにあった。
20世紀の法王たちは、進化論、唯物論、男女平等、産児制限などの現代化の荒波の中で、内部改革には牛歩の歩みだった。一方、世界平和や外交問題では、驚くべき柔軟性を発揮した。ヨハネ・パウロ2世がイラク戦争に直ちに反対声明を出したことで、西欧の政治指導者や国連事務総長、イラン特使まで、法王謁見のためにバチカンに飛んで来たことは、吟味する必要がある。
また、短期間に大衆的人気に迎合する恐れがある民主主義に比べて、法王の終身制とその選出の集団合議制が持つ長所もある。長期間一貫したリーダーシップの発揮を裏付け、その失敗を補完する新しいエリートの充員を集団的指導力の中で見出しているためだ。
原題:Chronicle of the Popes(1997)
Weltmacht Vatikan(2004)
confetti@donga.com