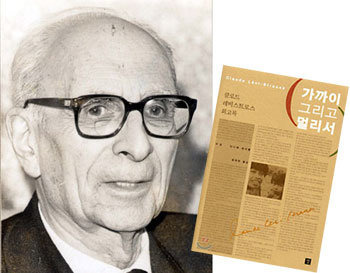
人類学を専攻する人や人類学の書物に少しでも関心を持っている人にとってクロード・レヴィ=ストロースは、いつもひどく薄情な人だった。なぜなら原本はもとより、翻訳を何回読み返しても、一体何を言わんとしているのかさっぱり理解できず、絶えず私自身を責めるように仕向けた張本人だったからだ。たかだかいくつかの解題に目を通しただけで、まるで原本を読んだかのごとく大げさに言いまくったことも、何と多かったことか。ところがこの本は、私にとってそうした卑怯さを思い切り振い落とさせてくれた。
この本は、ディディエ・エリボンという鋭い観察力を持った学術記者が、レヴィ=ストロースという巨大な人類学者の頭と胸の中に秘められた数々のストーリーを、まるで華麗な紋様の織物をするため、様々な縦糸と横糸を編むような形で構成されている。ここに、エリボン氏は高度に訓練された人類学者であり、レヴィ=ストロースの研究は主な情報源となって、一つの民族誌、すなわちエスノグラフィー(Ethnographie)を完成したのである。
この本の内容は、大きく4つに分けられる。
第1に、レヴィ=ストロースが生涯に学問的な交流していた人々との関係を築く過程で交わした学問的な霊感の理解を通して、現代思想史の大きな流れを理解することができる。フランスの思想家だけでなく英米学者らと生涯続いた友好的または非友好的関係は、様々な形で、レヴィ=ストロースの学問に莫大な影響を及ぼしている。氏の口を通して言及される思想家の名前を一々挙げることすら手に余るくらいだ。カントやヘーゲルはもとより、ルソー、マルクス、フロイト、ラカン、ヤコブソン、ブローデル、ディメジル、ベイユ、サルトル、ブルトン、ベルグソン、エルンスト、ボアース…。
第2に、レヴィ=ストロースの学者としての生涯に焦点を当てて一人の人間、一人の学者、そして社会の構成員の一人として、いかに自らの地位との釣り合いを取ってきたのかを考察しているが、これは彼が直接書いた本からは容易に接することのできなかったものだけに、非常におもしろい。哲学から民族学に専攻を変えて南米のインディアン文化に関心を抱くようになった背景、生涯大学の正式教授として在職することができず、教授になることをほぼ諦めたものの、ついに3回目の挑戦でコレジュード・フランスの教授に任用された過程、社会主義に心酔しながら社会参加と学者としての葛藤と、「68年学生革命」に対する批判、「神話論」の4巻を完成するために20年あまりの歳月を、厳格かつ苦痛に満ちた日常と戦った記憶などを挙げている。これをレヴィ=ストロースは、ドンキホーテ主義の本質と表現している。つまり、過去を再発見しようとする粘り強いニーズが、人生の倦怠感に対する自己防衛を可能にしたとみているのだ。氏の表現によると、作業のため常に不安を感じているものの、作業をしながら時間の流れを感じずにすんだというのだ。
第3に、数多くの著作物のなかで示された様々な概念に対する、レヴィ=ストロース自らの具体的な説明がなされている。社会記号としての「女性交換」、人間の普遍的な同質性を根本的に追求する上で影響を及ぼした心理学と精神分析学、実践的実存を理解する上で必須とされたマルクシズム、本人の意図とは違ってはなはだ歪曲された形で使われており、不満を感じていた「構造」の概念、主体と客体とを引き離して説明しようとしたサルトルの実存主義に対する批判、近代的な考え方とは明らかに異なるものの、現在においても確かに存在する「神話的思考法」(ブリコラージュ・Bricolage概念として説明)を通して、感性界と知性界の対立を超えた設定を試みた「具体の科学」、連関関係が規定されなければ使うことのできない「比較方法」などに関するものがある。
そして最後に、レヴィ=ストロースが生涯をかけて築き上げた人類学という学問に対する、限りない愛情を理解することができる。彼は、ルソーこそ知性界と感性界の連合を追求した人間科学の創始者であると称している。即ち、「マルクスとフロイトは私を思惟する者にしたが、ルソーを読んでいると私は熱狂する」という彼の表現は、ルソーを通じて最も大本となる人類学的霊感を得たことを示唆している。
彼は、全ての民族学者は自我を経て自我から離れなければならないために、自らの「告白」を書くとしている。民族誌学的な経験は、研究者自身を離れることに対する経験的な探求であるがゆえに、自我を求めて異国の地を冒険するというのだ。自分自身をあまりにもよく知っていると考えるなら、あえて厳しい冒険を求めて異国の地を訪れたりはしないはずだから。人類学者の書く民族誌は、正に自分を探すためであるというこの言葉は、生涯、自分を捜し求めてさ迷うしかない人類学者の、切なる自己告白に違いないだろう。人類学は、悲しいことに全てに対する解答を持つことができないとしながらエリボンとの対談は終るが、この言葉ほど自らの学問に対する根強い愛着を表現できる言葉は、他に見出せないだろう。
氏の学問的な情熱には頭の下がる思いである。ただ、その前に横たわる時間がもどかしいだけだ。
リュ・ジョンア ソウル大学講師(人類学)







