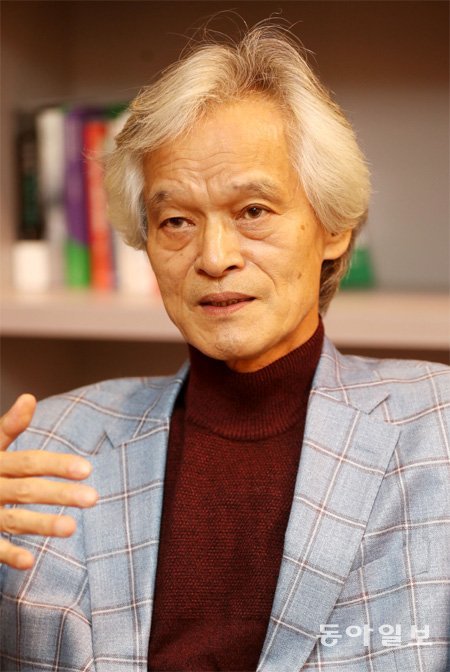
社会学者として生き、3年前に突然長編小説二編を書いた。学者として40冊以上の本を書いたが、時代が流れれば知識も共に流れてしまい、虚しくなったためだという。宋虎根(ソン・ホグン)浦項工科大学(ポステック)客員教授(64)が、『人民の誕生』(2011年)、『市民の誕生』(13年)に続き7年ぶりに『国民の誕生』(民音社)で「誕生」3部作を完結させた。先月27日、ソウル鍾路区(チョンロク)の東亜(トンア)メディアセンターで会った宋氏は、「『誕生シリーズ』は10年以上の間、研究の末に書いた本なので、虚しさを感じない本だ。他の本を書いても、いつもこの本を終えなければならないという負い目があった」と話した。
シリーズを貫くテーマは、朝鮮末期と日本帝国主義時代の韓半島の公論の場だ。宗教、政治(社会運動)、媒体(文芸)の3つの軸の公論の場に現れた人民、市民、国民の意識の発展の様相を追う。『人民の誕生』では、ハングルの拡散で平民の間に談論の場が発生し、人民に発展した過程を、『市民の誕生』では人民を越えて近代市民に変貌していく過程を追った。
今回の本では、1905~19年の苛酷な日帝弾圧の下、密かに芽生えた市民意識に民族主体性が加わり、国民意識を持つようになる過程を分析した。宋氏は、高宗(コジョン)が崩御し、人民に「滅びゆく国を私たちがつかまえなければならない」という主体意識が生まれたと見た。文芸と宗教の公論の場で芽生えていた市民意識が民族性と歴史性に出会って抵抗運動に変貌し、3・1運動で花を咲かせたと分析した。宋氏は、「市民と歴史性が結合すれば国民になる」とし、「歴史的に市民社会から国民国家に進入する時、革命や戦争が起こるケースが多いが、韓半島では3・1運動が起こった」と強調した。
宋氏は、当時の小説において文芸の公論の場の糸口を見出した。宋氏は、「日帝弾圧で小説しか読むものがなかった。当時1700万人口のうち2割が新小説を読んだだろう」とし、「読書を通じて対話がなされ、公論の場が形成された」と指摘する。特に市民のアイデンティティを持つ主人公が登場する李光洙(イ・グァンス)の小説『無情』(1917年)が重要な役割を果たしたと分析した。
さらなる重要な公論の場の軸である宗教に対して、宋氏は「市民宗教」と命名した。宋氏は、「フランスの社会学者エミール・デュルケームが説明したように、人間宗教が聖なら、市民宗教は俗だ。宗教を世俗化したのが市民倫理の発現だ」とし、「宗教の公論の場は市民を培養するインキュベーターだった。ここに民族アイデンティティが加わり、抗日運動、すなわち3・1運動に貢献した」と強調した。
このシリーズを執筆してきた13年間、公論の場を深く掘り下げた宋氏にとって、現在の韓国社会の公論の場はどのような姿だろうか。宋氏は「文在寅(ムン・ジェイン)政権は意見が違う人を『正義が分からない人』と決めつけて壁をつくった」とし、公論の場の不在を指摘した。そして、「指向と経歴が同質の城(大統領府)の中の執権勢力が、1980年代から守ってきた『彼らの民主主義』を守護するとし、むしろ民主主義を傷つけている。外部から攻撃されれば門を閉ざした朴槿恵(パク・クンへ)政府と結果的に同じになった」と批判した。
現代を背景にする誕生シリーズ4作目を期待していいかと問うと、宋氏は「まだ早い」と言った。そして、「韓国戦争後の多宗教社会への発展などを考えると、その後の公論の場を研究することは途方もない課題」とし、「旧韓末開化の思想家、兪吉濬(ユ・キルジュン)を素材にした小説を書いてみようと思う」と話した。
崔고야 best@donga.com







