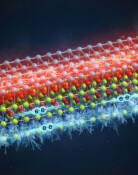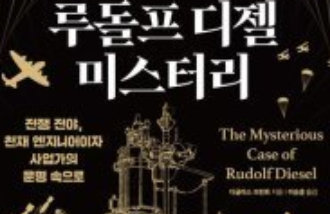「1人の天才が偉大な発明品を作り出したという話は神話にすぎない。電信機(サミュエル・モールスが発明しなかった)、電球(トーマス・エジソンが発明しなかった)、飛行機(ライト兄弟が発明しなかった)のような偉大な発明品は、歴史を輝かせた一人の発明家ではなく、多くの人が集まって成し遂げたものだ。それがまさにグループ・ジーニアス(Group Genius)だ」
個人の天才性ではなくグループ・ジーニアス、すなわち集団の天才性が世の中を導くという話。そのため、組職が発展するには集団の天才性を発揮できるように絶妙の協業システムを備えなければならないというのが、『グループ・ジーニアス』の要旨だ。
著者キース・ソウヤーは、米国の心理学者であり経営コンサルタント。集団の天才性という概念は、劇団とジャズ楽団に対する観察から生まれた。1990年代、ある劇団俳優たちの即興演技とアドリブ、あるジャズ楽団の演奏者たちの即興の演奏を見て、著者はひらめいた。即興で演技、演奏をしていると、ミスや予想しない突発状況が絶えず発生する。その突発状況にうまく対処すること、それがまさに成功の鍵だと考えた。そのためには、1人だけの能力では不十分だ。
すべての俳優と演奏者が自分の能力を発揮して助け合い、一瞬一瞬の状況に絶えず対処していかなければならない。集団の天才性も必要で、構成員の協業も必要だ。これがまさに著者の悟りだった。
ここで言う協業は、よく言われる協業とは違う。一瞬一瞬の予想できない問題と状況に対処しなければならないため、その協業は即興的かつ瞬間的でなければならない。突発状況に対処する即興性がさらなる創造的洞察力を引き出すというのが、著者の信念だ。
ある人はこのように問い返すかもしれない。「瞬間的で即興的にひらめく創造的な考えも、結局は一個人から出たものではないか」と。これに対する著者の反論は確固としている。「一個人の創造的洞察力も、実は以前にほかの人々と共有した多くの考えが思い浮かぶ時に生まれる」と。
著者はこの主張を裏づけるだけの多くの事例を紹介する。1970年代後半、現金自動預け払い機を設置して、預金を2倍以上引き上げたシティバンクの驚くべき成果も、実は多くの人の小さなアイディアが協力の過程を経たことにより可能だったのだ。
日本のホンダの小型バイクの米国市場席巻も、即興的対処のお陰だと著者は説明する。米国市場で、ホンダの大型バイクに予想しなかった技術欠陥が発見された時、小型バイクがそれに取って代わるという即興的な果敢さが効果を生んだのだ。
著者は、組職がグループ・ジーニアスを発揮するためには、即興的協力システムが必要だと強調する。即興的協力は、一瞬一瞬の小さくて絶え間ない変化を持続的に追い求める過程でなければならない。それは、考えが柔軟であってはじめて可能になる。
考えが変われば、世の中も変わるもの。同書の最大の魅力は、集団の創造性、協業と革新に対する著者の新しい見方だ。
kplee@donga.com