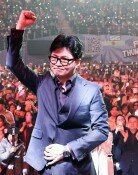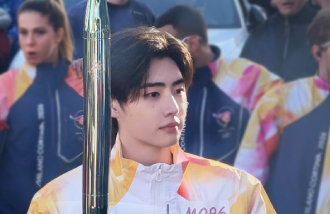芸術界に吹き荒れるAIブーム、「人間の芸術」が持つ意味
芸術界に吹き荒れるAIブーム、「人間の芸術」が持つ意味
Posted July. 06, 2023 08:14,
Updated July. 06, 2023 08:14
世界3大クラシックコンクールに数えられる「エリザベート王妃国際音楽コンクール」は、毎年異なる楽器でコンクールが行われる。そのため、楽器別では4~5年周期で開催されている。昨年、2017年以来5年ぶりに行われたチェロ部門のコンクールで笑えない事件が起こった。当時3位に入賞したエストニア出身のチェリスト、マルセル・ヨハネス・キッツのファーストラウンドの競演の時だった。
フランス出身の作曲家アンドレ・ジョリヴェのノクターンを1曲目に選んだ彼は、日本人ピアニストの薗田奈緒子のピアノ伴奏に合わせて、叙情的なチェロの旋律を披露していた。事件は、演奏が始まって6分34秒後に起こった。紙の楽譜ではなく電子楽譜を使用していた薗田のタブレットPCが突然作動しなくなったのだ。楽譜を覚えていなかった薗田は慌て、タブレットPCの画面を指で叩いていた。チェロとピアノの協奏曲だが、20秒間、ピアノの旋律は停止状態に近かった。この事件は、クラシックファンの間で「すべてのピアニストの悪夢」と呼ばれている。
このハプニングが再浮上したのは、最近、文化界に吹き荒れる人工知能(AI)とロボットのブームによる。国立バレエ団が今月1、2日、ソウル芸術の殿堂CJトウォル劇場で披露した「フィジカルシンキング+AI」は、人間とAIが作り上げた作品だった。国立バレエ団の首席ダンサー出身のイ・ヨンチョル指導委員は、チャットGPTにキーワードを与え、「一人の人生とAIの誕生を織り交ぜた短い物語を書いてほしい」と依頼した。これをもとにイ氏が作曲及び振り付けAIを活用して音楽と振り付けを構成した。先月30日の国立国楽管弦楽団の公演では、人間(指揮者チェ・スヨル)とロボット(エバー6)が同時に指揮者として登場した。ロボットはなんと2曲を単独指揮した。驚くべき光景だった。しかし、共に指揮に立ったチェ氏は、「ロボット指揮者が視線交換による団員とのコミュニケーションなどでは、人間に勝てないことを体感した」と告白した。
先ほどのタブレットPCの電子楽譜の話に戻ろう。韓国国内の演奏会で演奏者が初めて電子楽譜を使用したのは、ピアニストのソン・ヨルウムだ。2011年12月、錦湖(クムホ)アシアナのソリストの舞台で彼はベートーベン交響曲「合唱」第4楽章の楽譜をタブレットPCに入れ、自分で楽譜をめくりながら演奏して話題になった。10年経った現在、電子楽譜が人気を博し、演奏者の代わりに楽譜をめくる人、「ページターナー」の領域はますます狭くなった。しかし、昨年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで薗田が電子楽譜ではなくページターナーと呼吸を合わせていたら、「すべてのピアニストの悪夢」のような不名誉な言葉は生まれなかったのではないか。
いくらAIなどの技術が浸透しても、芸術の感動は人の指先から生まれる。演劇などの舞台芸術では、同じキャラクター、同じセリフを演じても、俳優が誰であるかによって観客が感じる「演技の味」が変わる。フレディ・マーキュリー(1946~91)の声を学習したAIがキム・グァンソク(1964~96)の「三十歳の頃に」を歌って話題になったが、原曲の歌手が作り出した感動は引き出せなかった。それが芸術の醍醐味だ。機械が学習で人間の感性に追いつくには限界がある。AIブームの中で「人間の芸術」について改めて考えさせられる。