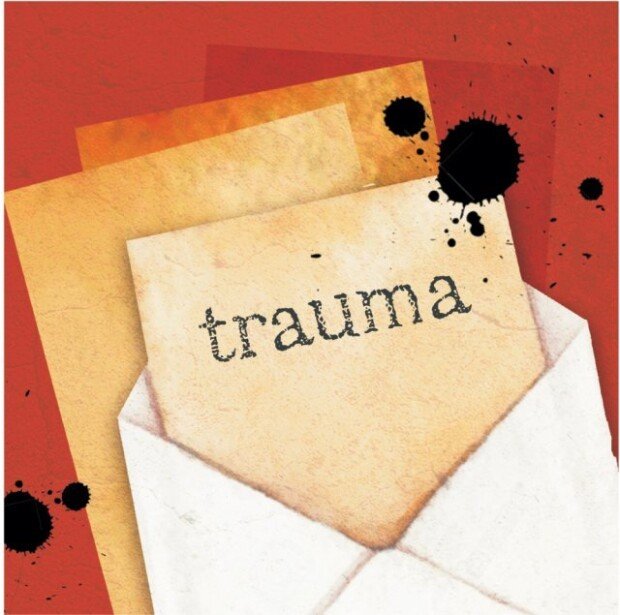
精神分析学者ドリ・ラウブは、トラウマを「始まりも終わりもなく、以前もなく、中間もなく、以後もない出来事」と定義する。時間が経っても過去の出来事に縛られているトラウマの恐ろしさを強調した言葉だ。フランツ・カフカの「父への手紙」は、これを生き生きと証言している。
手紙を書いたのは1919年11月のこと。47ページに達する長文の手紙だが、その要旨は最初の文章に表われている。「お父さんは最近、私がどうしてあなたをまだ恐れているのかと聞きました」。36歳にもなったのに父を恐れるとは。だからといって、彼は幼い頃、ひどく殴られたわけではなかった。むち打ちは要らなかった。父の怒鳴り声、赤らんだ顔、椅子にのせたショルダーストラップだけで十分だった。むち打ちを暗示するこうした兆候は、むち打ちよりも恐怖だった。
父はそういう男だった。ある晩のことだった。幼いカフカは、ベッドでのどが渇いたとつぶやいた。のどが渇いたというよりは甘えたのだ。しかし父親は激怒した。彼は、寝巻きだけ着ている子供を乱暴な手でひっぱりあげてベランダに連れて行き、ドアを閉めてしまった。その後、子どもは巨大な体の父親が、ベッドにいる彼をいきなりひっぱりあげてベランダに引きずり込む悪夢を見た。成年になってもそうだった。「私の文章はすべて父に関するものです」と言ったほどだ。
手紙に出てくる父の姿がどこまで事実に合致しているかは分からないが、36歳の彼の内部に傷付いた子供がいたことだけは確かなようだ。手紙はその子の泣き声だった。もしかすると、その泣き声は癒しの第一歩だったのかもしれない。ところが残念にも、その泣き声は父の耳にとどかなかった。父に渡してほしいという手紙を読んだ母が、あまりにも胸が痛かったのか、息子にそのまま返したからだ。それから5年後、カフカはこの世を去った。「トラウマのつらい記録を後に残して…」







