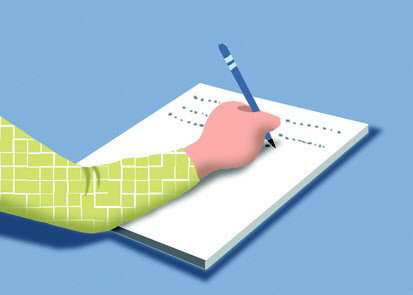
「書くことは個人的なことで、その幸せは言葉で表現することはできない」 ―パトリシア・ハイスミス
タニア・シュリーの著書『女性が本を書く場所』で紹介された米国作家パトリシア・ハイスミスの言葉だ。
生涯小児科医として働きながら詩を書いたウィリアム・カーロス・ウィリアムズは、「片方が私を疲れさせるとき、もう片方が私を休ませる」と言った。診療室でシャーロック・ホームズを生み出したコナン・ドイルや、小説『城砦』のA・J・クローニンもそうだっただろう。私自身も処方箋を書いたり、脚本を書いたりして暮らしている。漢方医として診療する中で出会った多くの人々によって私の物語の世界も成長してきたので、作家としての私を育てたのは、漢方医としての私だろう。
全く異なる2つの世界が「書く」という行為を通してつながるということが、私には時々驚異に思われる。書くという行為は一つの世界を開く作業であり、一人の人間への探求の過程である。処方箋を書くために、私は脈を診るだけでなく、ちゃんと食べているか、よく眠っているか、痛いところはないか、この症状はなぜ今現れたのか考える。一人の体質と個々の状況というすべての変数に最適な処方箋を「書く」ために悩むのだ。脚本を書くときも然り。主人公はどのような人なのでこのような行動をし、他の人物とはどのような関係を築くのか、考えなければならない。
そうして一人の漢方薬の処方箋を書くことと劇のワンシーンを書くことは、とてもよく似ている。体質と薬材の特性を調和的に構成した処方箋を書き、薬材一つ一つが互いに相乗効果を発揮できるように丁寧に煎じなければ薬効を発揮できないように、脚本も人物と事件が密に絡み合うようにしなければ、見る人の共感を得ることができない。一人で暗い机の上で孤独に長い時間を過ごさなければならないが、良い処方箋を書いて診療室を出る時、「これだ!」と思うシーンを書いて楽しく机を離れる時、その幸せは言葉では言い表せない。来る春には、この文を読む人々に書くことを処方してあげたい。優しい春が残酷になる日があるなら、日記を書いてみてはどうか。







