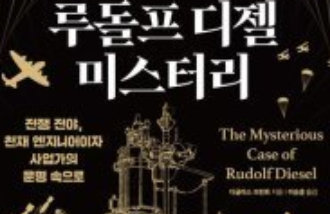「13世紀に東アジアも温暖期だった可能性」
「13世紀に東アジアも温暖期だった可能性」
Posted November. 08, 2023 08:23,
Updated November. 08, 2023 08:23
気候環境が韓国の歴史に与えた影響にスポットライトを当てる学術大会が開かれる。韓国生態環境史学会と韓国生態環境史研究所は11日、ソウル市中区の東国(トングク)大学で、「13世紀東アジアの気候変動と自然災害」をテーマに秋季学術大会を開く。
釜慶(プギョン)大学史学科のキム・ムンギ教授は学術大会で、「温暖期の発見:13世紀東アジアの気候変動」を発表し、東アジアが13世紀頃、温暖期だった可能性を提起する。欧州の学界では10~13世紀を「中世温暖期」と規定する見解が支配的だが、東アジアについては関連研究が比較的少ない。キム教授によると、元の農業技術書『農桑輯要』には、13世紀初頭、柑橘が現在の北方限界(南京地域)より北の河南省唐河県や沁陽県などでも栽培されたと記録されている。
キム教授は、「最近、中国の学界では13世紀を明確な『温暖期』と規定している」とし、「高麗時代の建築物や遺跡などの樹木から気候変動情報を科学的に分析し、中世東アジアの気候変動史を研究する必要がある」との認識を示した。
これに関連して、江原(カンウォン)大学のキム・テギ教授は「13世紀中国の異常気候と災害」を発表する予定だ。
このほか、延世(ヨンセ)大学医学研究所のイ・ヒョンスク教授は、「新菩薩経と勧善経で見た唐高宗時代の病気と人口」を発表する。唐代の経典を通じて7世紀頃に東アジアに広がった病気を分析する一方、新羅と唐が連合した羅唐連合軍を通じてこのような病気が韓半島に流入した可能性を提起する。
イ・ソヨン記者 always99@donga.com