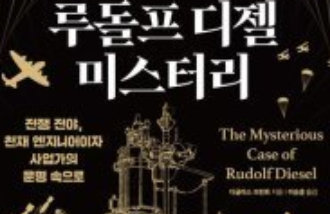休みの季節の終わった9月の第1週、オフィスごとに休みの後遺症にかかった人々が何人か目に付く。休みの素敵な思い出が頭から離れない人々もいるだろうが、睡眠不足や生体リズムの変更で、仕事が手につかない人たちも多い。8月末、ある求職サイトがサラリーマンを対象に調査を行った結果、回答者の82.9%が休みの後遺症を経験したことがあると答えた。「休みがもっとも必要な人は休暇から戻ってきたばかりの人だ」という言葉もそれほど間違ってはいない。
◆大勢の人々の休みが集中する夏場よりは、自分の必要な時期に休暇の取れることを願う。しかし、ニューヨークタイムズの最新号では、いつでもほしいがままに休みが取れる「開放休暇制(un−vacation−policy)」は、それほど望ましい制度ではないと報じた。1990年代初頭、開放休暇制を導入したIBMの場合、仕事と休暇の境界線が曖昧となり、35万人の職員が休暇機関にも緊張をほぐせなくなり、仕事への負担がかえって増えたという。
◆開放休暇制は平日と土日曜日とをまとめて、短い休暇を数回にわたって取ったり、一度に2週間をとってもいい制度だ。明日から休みを取りたいと、今日上司に話しても気兼ねする必要はない。さらに、会社では社員が使った休暇日数すら集計していない。このような幻想的な制度がどうして失敗に終わったのだろうか。結論は簡単だ。職員は仕事の成果から自由でないからだ。1週間後に試験を控えている生徒に、1週間の休みを与えたからといって、うれしくないのと同様だ。
◆米国文化を観察して、「カルチャー・コード」という本を出したフランスの文化人類学者クロテル・ラファュは、米国人にとって職業は、「アイデンティティ」だと分析した。仕事がなければ、自分と言う存在もない。米国の億万長者たちが、膨大な富を築いたのにも、より多くの金を稼ぐために努力したからであり、ベビーブーム世代が引退後にも仕事を求める現象も、そのような延長線上で理解できる。効率性を重視する職場文化なら、われわれも米国人には劣らない。やや休みの後遺症はあるものの、「短くて充実した」休みが、われわれにはより適しているようだ。
鄭星姫(チョン・ソンヒ)論説委員 shchung@donga.com